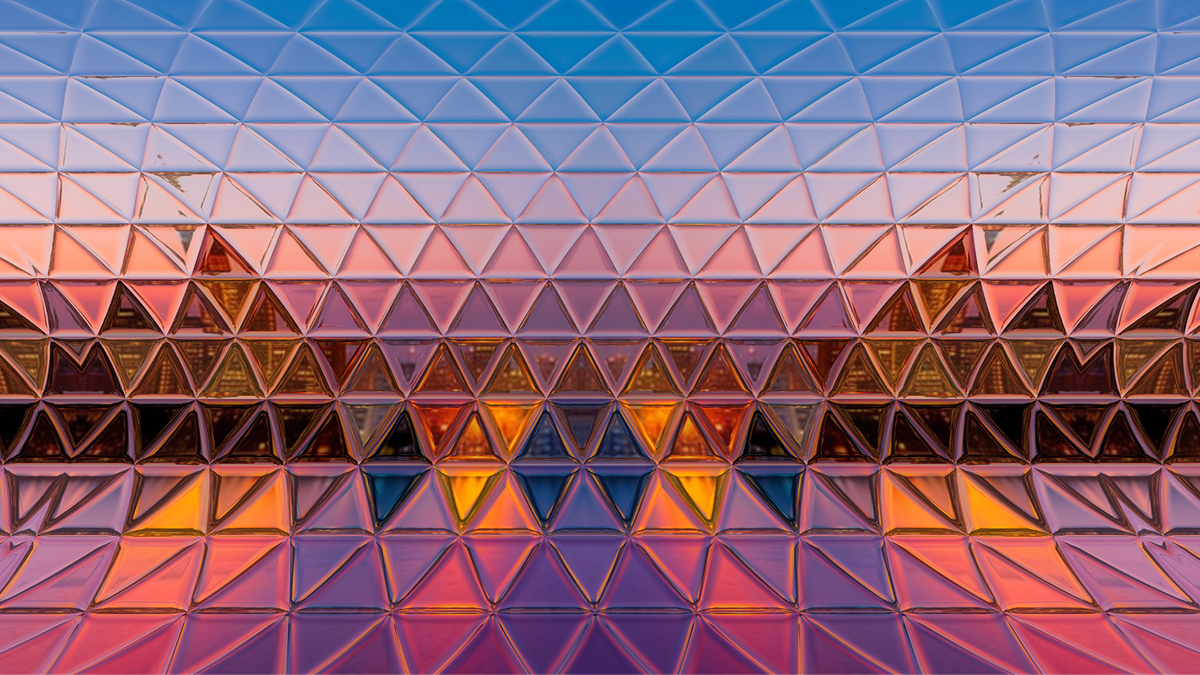
要旨
- 債券セクターが堅調に推移し、米連邦準備制度理事会(FRB)が利下げサイクルを再開した環境下、経済成長の継続とインフレの緩やかな鈍化を見込む。労働市場への懸念や低所得層の弱さは存在するものの、消費者全体は安定しており、財政政策による景気刺激が下支えになると期待される。
- 今回の四半期投資戦略会議(IQ)では、トレンドを下回る成長の発生確率は45%とし、引き続きメインシナリオとした。そのほか、トレンドを上回る成長の発生確率を40%に引き上げ、景気後退および危機の発生確率はそれぞれ10%、5%に据え置いた。
- メインシナリオでは、FRBが来年2回の利下げを実施し、10年物米国債利回りは3.75%から4.25%の範囲になると予想する。
- トレンドを上回る成長の発生確率を引き上げたのは、経済の力強さを示す兆候が多いからである。政府のビジネス重視の姿勢や、AI主導の設備投資ブームが投資と生産性を押し上げ、企業収益の再加速につながる可能性がある。
- このような環境下、当チームでは、キャリー重視の投資を選好する。具体的には、投資適格社債、ハイ・イールド社債や転換社債、新興国債券、証券化商品(エージェンシー・モーゲージや商業用不動産担保証券など)である。
当チームの12月のIQはホリデーシーズンのはじまりとともに、新たな本社である270パークアベニューで開催された。FRBが再び利下げを実施し債券市場が年初来で目覚ましいリターンを記録したことから、本来であれば祝祭ムードのはずだった。しかし、当然ながら投資に関する懸念が意識され米国の労働市場や消費者の健全性、根強いインフレ、中央銀行の独立性、そして人工知能(AI)のコストと便益について疑問が浮上した。
要するに、足元の市場と経済の状況は「うますぎる話」なのではないかという疑念が生じたのである。
我々はいつものように、膨大なデータを徹底的に分析し、それらを基に疑問への答えを導き出した。「解放の日」の影響は最悪期を脱したのか、さらに目覚ましい市場リターンが待ち受けているのか。それとも、市場は実現不可能な、理想的な経済状態を織り込んでいるのか。
マクロ経済の動向
我々は、FRBの二重の使命である「完全雇用(経済成長)」と「物価安定(インフレ)」に焦点を当て、今後の金融政策の道筋を探ろうとした。米国経済は力強さの兆候を数多く示している。まずホワイトハウスに注目すると、現政権が成長重視かつビジネス重視であることは明らかである。米国企業も関税政策に対応し、前進しているように見受けられる。企業は価格上昇の一部を吸収し、また残りは消費者に価格転嫁している。企業の利益や売上高見通しは、ここ数四半期で最も力強い水準にあり、今後再加速の可能性もある。
所得下位20%の層には消費の弱さが見られるものの、消費者全体の状況は安定しており、「一つの大きく美しい法案(OBBBA:One Big Beautiful Bill Act)」の税還付という形の財政刺激策も、数か月後に控えている。しかしながら、我々は労働市場の軟調さについて懸念を抱き続けている。企業は、関税やAIが自社の事業モデルに与える影響が明確になるまで、単に採用を一時停止しているだけかもしれない。しかし現実には、雇用者数の伸びは鈍化し解雇の発表も増加しており、失業率は4.6%と、2023年4月の最低水準から1.2ポイント上昇している。労働市場データが不安定であるため、FRBの政策担当者は「完全雇用」の目標を達成していると自信を持って断言することができない状況である。
同時に、インフレは依然として根強く、FRBがコア個人消費支出(PCE)で目標の2%を達成してから、ほぼ5年が経過している(現在は前年比+2.8%)。FRBメンバーの間では、インフレへの懸念が高まり、さらなる金融緩和に抵抗感を示す者が増えている。それにもかかわらず、我々は来年に追加で2回の利下げが実施されると考えている。利下げを後押しする要因としては、FRBが中立金利を3%と示し続けていること(現在の政策金利は3.625%)、労働市場が軟調であること、サービスおよび賃金のディスインフレ傾向が続いていることが挙げられる。さらに、近く発表される見込みの新しいFRB議長は、ハト派寄りの姿勢を取ることが確実視されている。このような状況下では、米国10年債利回りは3.75%から4.25%の範囲に留まる可能性が高いと考える。
世界のその他の地域の政策と成長の軌道は、よりまちまちの展開となった。英国のインフレ率が他の先進国経済並みの水準に収束し、労働市場の弱さが賃金成長を抑制する中、我々はイングランド銀行がFRBと同様に利下げに踏み切ると予想する。欧州中央銀行(ECB)は、インフレ率が目標水準にある一方で財政支出が増加し始めているため、政策を据え置く見通しである。オーストラリア準備銀行と日本銀行は、成長とインフレ圧力が続く中で利上げを実施すると見込まれる。中国は新興市場において依然として重要な存在であるが、他地域にも多くの投資機会が見込まれる。中国では、記録的な財の貿易黒字により、世界経済にデフレを輸出し続けるだろう。国内消費の弱さは、固定資産投資や来年のGDP成長率4.5%を支えるための財政刺激策によって部分的に相殺される見通しである。
全体として、我々は世界経済が関税の影響を吸収する力に感銘を受けた。また、AIの構築に必要な設備投資が短期的な成長と長期的な生産性向上の双方に有益であることを認識した。さらに、広範なディスインフレ傾向が今後も続くと考えている。このようなマクロ経済環境は、市場にとって好ましいものである。
シナリオ見通し
当チームは、トレンドを上回る成長の発生確率を20%から40%へと引き上げた。関税の影響はすでに過去のものとなり、米国と欧州では財政刺激策が進行中であり、AI関連の設備投資も加速している。成長が今後も堅調に推移すると考える一方で、インフレは依然として緩やかに推移する可能性があると見ている。消費者は明らかに価格に敏感になっており、これが企業の価格決定力を制限している。また、AI主導の生産性向上によって成長が加速しても、労働市場が再び逼迫するとは限らないと考える。
トレンドを下回る成長の確率は65%から45%へと引き下げた。依然としてメインシナリオであるが、「トレンドを上回る成長」との差はわずかである。緩やかなペースに留まる失業率の上昇と健全な経済成長に鑑みると、労働市場は時間をかけて正常化(足元の過去平均を下回る水準から上昇)すると考えられるものの、経済に大きな損失をもたらすことはないだろう。ただし、所得下位20%の層は依然として苦しんでおり、OBBBAが十分な効果を発揮してこの問題を解決できるかは不透明である。景気後退と危機の確率はそれぞれ10%と5%に据え置いた。金融緩和、財政刺激策、リスク資産の大幅な下落を容認しない政治スタンスに鑑みると、今の世界で経済収縮を想像するのは難しい状況である。
リスク
最大のリスクは、コロナ禍の世界的な景気刺激策や過去の中央銀行による量的緩和によって金融システム内に溢れている資金が、急激な成長とインフレの高騰という形で一気に噴き出すことである。利下げの効果はまだシステム全体に浸透しきっておらず、今後の財政刺激策が投資家心理(アニマルスピリッツ)を再び活性化させる上で大きな役割を果たす可能性がある。もし、インフレを抑制するはずのAI主導の生産性向上がまだ遠い未来の話であり、データセンターや電力網などの構築が短期的な成長を加速させる要因となる場合、インフレは急騰する可能性がある。我々はまた、世界的な財政規律の緩みにも注目した。これらが現実となれば、中央銀行は利上げ体制に戻らざるを得ず、資産価格の下落を招くことになるだろう。
他にも、上記よりはリスクが小さいと考えるが、経済収縮の可能性もある。企業がAI投資のリターンが得られにくいと判断すれば、支出の縮小や減損が発生する。株式市場は調整を余儀なくされ、失われた資本が景気の減速につながる。しかし、こうした事態には政策担当者が危機に至る前に対応すると見られ、現実的なシナリオだとは考えにくい。
債券投資戦略への示唆
安定した成長とインフレの緩やかな鈍化は、債券市場および資産価格全般にとって好材料である。当チームはキャリー重視の投資アイデアに強気な見方をしている。具体的には投資適格社債からハイ・イールド社債、転換社債まで、幅広い企業クレジットを選好する。デフォルト率の低さと企業収益の力強さも追い風となっている。新興国債券、特に現地通貨建て債券についても、高い実質利回りと通貨の上昇余地から投資妙味があると考える。
証券化市場も支持を集めた。政府系MBS市場は政府系機関1による後ろ支えがあるほか、安定した消費者の存在が住宅ローン市場や自動車ローン市場を下支えすると期待される。一方で意外だったのは、商業用不動産担保証券への関心の高まりである。オフィス物件市場を覆っていた不透明感は晴れつつあり、再開発が進行している状況である。
まとめ
グローバル経済と金融市場は、驚くほど良好な状況で年末を迎えている。関税や地政学的圧力の影響は薄れつつあり、財政刺激策が導入されようとしている。企業の関心は、今最も注目されているAIに向けられており、政策担当者は経済のいかなる下振れリスクにも備える姿勢を取っている。我々の方針は、そのような環境を活かしてさまざまな市場で利回りを積み上げ、バリュエーションの変化に応じて積極的にポジションを入れ替えることである。われわれにとってのホリデーギフトは、「2026年に非常に良好な債券市場のリターンが期待できるということ」である。
※本稿は2025年12月18日時点における当社グループの見解です。